個人事業主におすすめのバーチャルオフィス
個人事業主にこそおすすめしたいバーチャルオフィスのメリット、よくある質問、個人事業主の方のバーチャルオフィス利用例、成功例のインタビューなどを紹介

個人事業主として、あなたは自身の事業を成功させるために日々努力していることでしょう。
成功の一部は、可能な限り税負担を軽減することによって達成されます。節税の方法はさまざまですが、ここでは特に個人事業主にとって有益な手段を2つご紹介します。
一つは「青色事業専従者給与」制度を利用して家族に給与を支払う方法、もう一つは「確定拠出年金(iDeCo)」を利用した長期的な節税・資産形成です。
弊社はこれまで11年間、バーチャルオフィスを運営してきました。その中で多数の起業される方、フリーランスの方、個人事業主の方を見てきましたが、中には節税や将来の資産形成について入念に計画を立てている方もいました。
逆に、あまり考えていない人も多かったです。
そこで、この記事ではこれらの方法を適切に活用することで、より効率的な経済管理が可能となり、あなたの事業がさらに発展する手助けとなるでしょう。節税するためには、まず正しい節税の方法を知ることから始めましょう。個人事業主として効果的な節税方法を解説しますので、参考にしてください。

事業運営を進める上で、個人事業主の皆さんが注目すべき節税対策の一つが「青色確定申告」です。この申告方式とE-TAXなどを用することで、最大で65万円の所得控除が受けられ、大きな節税効果を期待することができます。
青色申告は、確定申告の一種で、きちんとした経理・会計を行い、所得税法で要求される帳簿を作成・保存している事業主が選択できます。通常の白色申告と比較して手間は増えますが、その見返りとして受けられる控除額は大きいです。
この制度を利用するためには、税務署に青色申告の承認を申請し、承認される必要があります。申請は年度始まる前(1月1日まで)に行う必要がありますので、早めに手続きを進めましょう。
また、青色申告を行う場合、必要な会計知識や手続きを理解し、適切な帳簿の作成と管理が必要となります。会計ソフトを活用する、または税理士などの専門家に相談することも有効です。
一見難しそうに感じるかもしれませんが、青色申告は節税対策として非常に有用です。しっかりと理解し、適用することで、事業運営をより健全で効率的なものにすることができます。
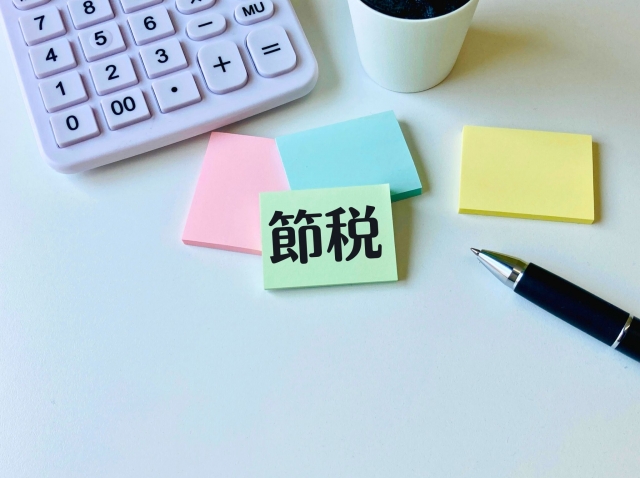
自宅を事業の中心地として活用している個人事業主は、家賃や水道光熱費などの経費をどのように分配するかという問題に直面します。これは、個人的な利用とビジネス利用の間でこれらの費用をどのように区分するかが難しいためです。これらの混在した支出に対して、ビジネスでの使用部分を計算し、それを経費として計上する方法を「家事按分」と言います。
たとえば、家賃の場合、家全体の床面積から、事業に使用しているエリアの床面積の割合を計算し、それを「地代家賃」として経費に計上することができます。水道や電気などの光熱費については、使用時間や使用日数を基準に分割します。正確な数値を出すのは難しいため、合理的な割合を請求額に適用して計算することが推奨されます。

携帯電話や自宅の電話FAXを利用する場合、も上記同様に通信費用も按分することができます。通信費に仕訳できる支出としては、電話代やインターネット料金、プロバイダの初期費用、ドメイン維持費などがあります。 通信費の場合は業務に利用している時間・日数で割合を求める方法が一般的です。
配偶者がいる個人事業主は、配偶者控除という税制上の優遇措置を利用できる可能性があります。
配偶者控除とは、納税者が法定の条件を満たす配偶者を持つ場合に適用され、一定の所得控除が可能となる税制上のメリットです。控除額は、納税者自身の年間所得総額と配偶者の年齢によって変動します。
配偶者控除の適用条件としては以下の4点があります。
具体的な控除額の例としては、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者が一般の控除対象者である場合、控除額は38万円となります。これは大きな節税効果をもたらすため、配偶者控除の適用条件を確認し、活用することを検討すると良いでしょう。
通常、家族間での給与支払いは経費に計上できません。これは家族が一緒に生計を立てている(共有の財布から生活費を捻出している)からです。しかし、実は家族にも給与を支払い、それを経費にする方法が存在します。それが「青色事業専従者給与」制度です。
青色事業専従者給与とは、青色申告を行っている個人事業主が、家族(専従者)に対して支払う給与のことを指します。つまり、配偶者や子供など、生計を一にしている家族が事業に全力で取り組んでいる場合に支払われる給与です。
しかしながら、青色事業専従者給与を認められるためには一定の条件が存在します。具体的な説明は省きますが、その点に注意が必要です。また、配偶者控除と青色事業専従者給与の併用はできません。
さらに、配偶者に対する給与を高額に設定すると、配偶者が所得税を支払わなければならなくなるため、その点にも注意が必要です。
通常、青色専従者給与は源泉徴収の対象となります。そのため、月額給与が88,000円以上になると、毎月の給与から源泉徴収を行う必要があります。そのため、源泉徴収の対象とならないように、月額88,000円未満の給与額を設定するのが一般的です。これにより、扶養の範囲内で、給与を約8万円と設定することが多いです。
確定拠出年金(iDeCo)は、個人事業主にとって大きな節税効果をもたらす年金制度です。iDeCoには以下の3つの税制優遇があります
個人事業主がiDeCoに拠出できる年間上限は81.6万円で、これらの拠出金は全額、所得税と住民税から控除できます。これにより、事業所得に対する税金が節約できます。

iDeCoは、毎月一定額の拠出金を自己選択の投資信託に投入し、その運用益を60歳以降に年金または一時金として受け取ることができます。個人事業主の場合、2022年4月以降の月額拠出上限は68,000円となっています。この制度を利用することで、老後の資産形成と節税を同時に進めることが可能となります。
会社員と比べて、個人事業主の老後受け取る年金は国民年金ベースで約6万円と、厚生年金の半分程度となるため少なく感じられるかもしれません。しかし、このiDeCoを活用することで、資産運用と節税の両面でメリットを享受することができます。
iDeCoの運用は投資信託に近い形で、リスクとリターンのバランスに応じて投資先を選択できます。ハイリスクな投資先を選んだ場合、元本割れのリスクがありますが、拠出金の税控除効果を考慮すれば、全体として見れば得する可能性が高いでしょう。したがって、個人事業主であれば、確定拠出年金(iDeCo)への参加は強くおすすめします。
このように、個人事業主の節税方法はいくつもあります。個人事業主として生き抜くためにはもちろん売上のことも大事なのですが、このように節税方法を工夫して、可能な限り出ていくお金を少なくすることも必要です。
それらを上手く組み合わせて最大限節税できるようにするのが大切です。
最後になりますが、弊社では これから個人事業主を始められる方に向け、簡単に安く利用できるバーチャルオフィスを運営しております。バーチャルオフィスとは初耳というと下記の記事を参照ください。
月額1,955円~ご利用可能ですので是非ご利用ください。