バーチャルオフィスのデメリットとメリットについて
契約する前に読んでおいてください。バーチャルオフィスにも利用できない業種があります

契約する前に知っておいてください
不安を解消

この記事を読まれている方は、恐らく初めてバーチャルオフィスを借りようと考えてい方が多いと思われます。
初めて利用される方にとっては、不安があるだけでなく、「どのようなトラブルがあるのか」を想像するのが難しい場合も多いと思います。
実はバーチャルオフィスを利用するにあたり、仕組みを理解しておけばトラブルや問題が起こることはそれほど多くありません。
しかし稀にですがバーチャルオフィスも人間が運営しているため、人為的なミスや不可抗力な事故が起こることが あります。
ここではバーチャルオフィス運営歴11年の弊社の実務経験やお客様から聞いた話をもとに、トラブルの経験について包み隠さず解説したいと思います。
「リスク」と「トラブル」についてはどちらも似たような意味合いがありますが、ここでは下記のように定義したいと思ます。
「備えあれば憂い無し」です。この記事を読むことにより、バーチャルオフィスにありがちな「トラブル」「リスク」「問題」を予め把握でき、将来的に起こるリスクやトラブルを回避できる可能性が高いので、是非最後までご一読ください。
通常企業間取引において「商談」「挨拶」などの訪問は電話やメールで事前にアポイントをとるのが慣例です。
しかし中には「ちょっと近くに立ち寄ったので」とか「ちょっと挨拶」などの理由でアポイント無しで突然来訪するお客様や取引先がいます。
このようなお客様や取引先がいたら要注意です。

これは弊社のお客様から聞いた「アポ無し訪問」のバーチャルオフィスのトラブルに纏わるお話です。
そのお客様(仮にA様とします)は求人広告など人材系の広告代理店を事業をおこなっており、以前は西新宿に拠点を持つバーチャルオフィスと契約していました。

営業スタイルは新規開拓が中心で、電話やメールなどで企業の人事担当者アポイントをとり訪問。求人広告の掲載出稿を提案するようなフローの営業でした。
ある時Aさんは中規模IT系の企業の人事担当者Bさんにアポをとりました。最初のアポは本当に挨拶だけのアポイントでしたが、その企業にまめに通い、継続的に役立つ情報提供して担当者Bさんとの信頼関係を築いていきました。
そういったAさんの努力もあり、ある時Bさんから「社内でエンジニアの募集することになった提案して欲しい」と提案のオファーを受けました。
Aさんは早速提案書と見積書を出したところ前向きに検討していただき、ほぼ受注になる寸前のところまでいきました。

しかしこの状況は突如として変わることになります。
ある日その人事担当Bさんが新卒の会社説明会で新宿に行くことになりました。たまたまAさんの名刺に記載された会社住所に近い場所での開催のため、挨拶がてらAさんのオフィスに寄ることにしました。
Bさんがオフィスを訪れたところ、そのオフィス住所の表札には別の会社のが表示されていました。しかもこのバーチャルオフィスは無人だったらしく、人の気配全くしないようでした。
人事担当者Bさんも「バーチャルオフィス」については全く知識が無かったため、恐らくものすごく怪しいと感じたのでしょう。
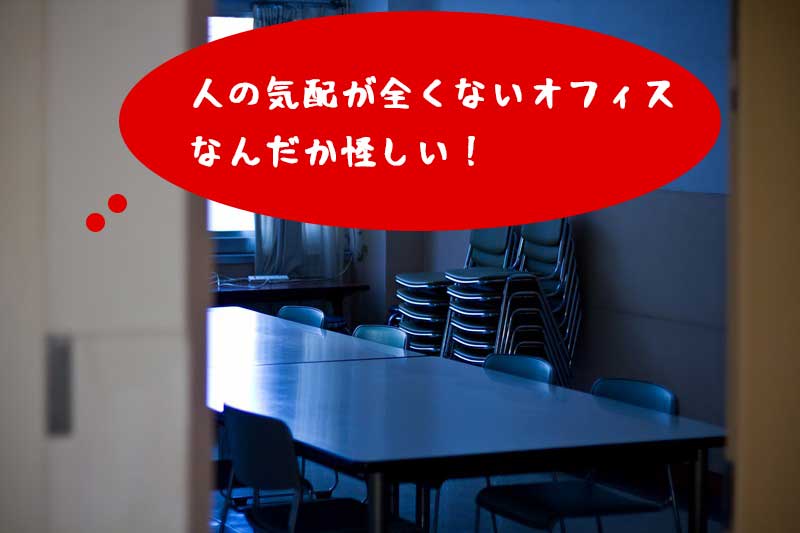
後日Aさんに電話をかけ「立ち寄ったところ別の会社が入居していた」ことを伝えました。慌ててAさんはオフィスは「バーチャルオフィス」で自分は普段は家で仕事しているという旨のことを伝えました。
人事担当者のBさんも「バーチャルオフィス」のことは理解したようでしたが、取引額が数百万単位だったということもあり、結局取引は成立せず、他の会社に契約がとられてしまったとのことです。
もちろんAさんのオフィスが「バーチャルオフィス」だったことが取引不成立の原因では無かったかものしれません。しかしBさんが訪れたオフィスは無人のためかあまり良い印象を残さなかったのは事実です。
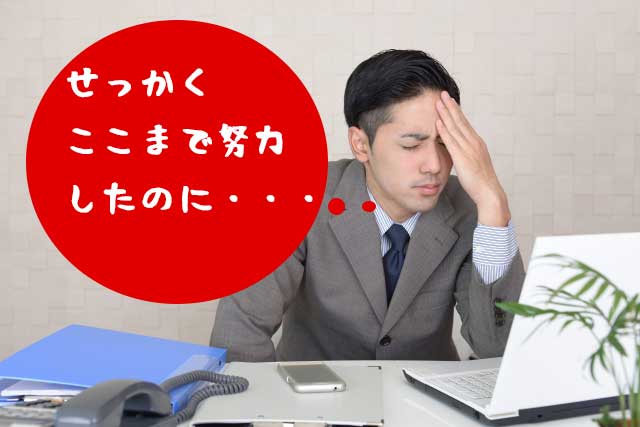

取引先やお客様にもよりますが、名刺の住所は予め「バーチャルオフィス」だと伝えた方がいい場合があります。大事な取引先ほど「バーチャルオフィス」を利用していると告げた方がいいでしょう。

郵送物が「バーチャルオフィス」に送られてきているのに転送されなかったり、遅れたりすることは、誤送などこのバーチャルオフィスでも起こっている代表的なトラブルです。
お恥ずかしい話ですが弊社でも過去にございました。
このような誤送や遅送のミスが発生する理由は、毎日大量の郵便物が届き、それらが全て人の手によって処理されるからです。
バーチャルオフィスは安価で契約できる半面、一拠点当たりのバーチャルオフィスの契約数は数百件以上、多いところで1,000件近い契約数なっている拠点もあります。
そうすると毎日もの凄い数の郵便物がそのバーチャルオフィスに届きます。

バーチャルオフィスの業務フローは郵便物が届いたら、まずどのような郵便物が届いたか契約ユーザーに連絡します。そして届いた郵便物については契約者ごとに仕分けして保管します。その後郵便物をまとめ契約者に発送します。
業務過程での郵便物の仕分けと発送は人間が行う作業であるため、人為的なミスや間違いが発生します。
絶対にあってはならないミスなのですが、似たような名前の会社がある場合や契約名義と違う宛名で郵便物が届く場合もありそんな場合誤送や遅配に繋がる場合もあります。

もし重要な郵送物が届くと分かっていた場合、予めその旨をバーチャルオフィスに伝えておくことをお薦めします。
バーチャルオフィスを利用している場合郵送物の受取が若干遅くなります。なぜなら、郵便物は一度契約したバーチャルオフィスに届いてから転送されるためです。
このタイムラグが原因で支払い関係に支障をきたす場合があります。
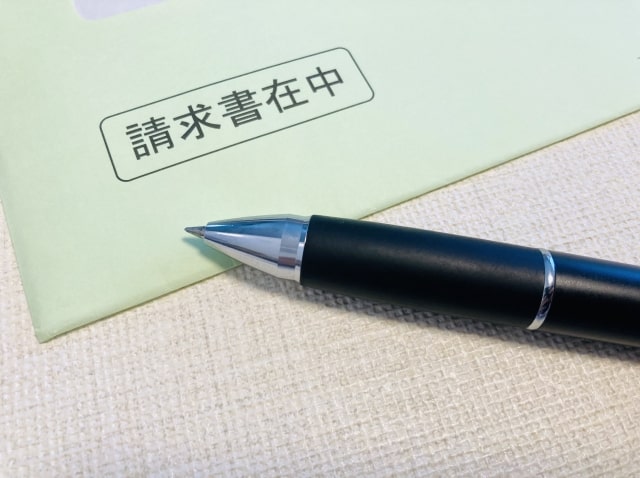
多くのバーチャルオフィスでは、郵便物はすぐに転送されず、月や週ごとに決まった日にまとめて発送されます。
そのため郵便の受け取りにタイムラグが発生します。 通常の郵便物だとそれほど問題にならないのですが、これが請求書など支払い関係の場合受け取りが遅れるため、支払い期限まで払えないといったトラブルが発生する可能性があります。支払いが遅れてしまうと取引先の信頼関係にも影響します。
最近では請求書の電子化も進み、請求書などが郵送で送られてくるケースは少なってきましたが、それでも書面による請求書の郵送は多く、請求書の他にも、税金納付書、社会保険納付書など支払いに関する郵送物は結構多いのです。最低でも支払いに関する郵便物だけは充分に注意することが必要です。


請求書関係はいつ頃届くか把握して、もし受取が遅れそうなら、すぐに郵便物を転送してもらうように しましょう。
社名変更や個人事業主の屋号変更などで会社名を変更された場合、変更した社名をバーチャルオフィス運営会社に連絡しないと、郵送物がそのまま送り主に返される可能性があります。
原則どこのバーチャルオフィスでも契約社名以外の宛名で郵便物が届いた場合、郵便物を受け取らず、そのまま郵便局に引き取ってもらい送り主に「宛先不明」ということで返送されます。

そのため会社名を変更してその旨をバーチャルオフィスに通知しないと郵便物が返送されてしまう恐れがあります。
これはどちらかというと法人より個人事業主の方が多くみられます。というのも個人事業主の場合、屋号の変更は簡単にできるからです。
また個人事業主の場合、バーチャルオフィス契約時に屋号を決めておらず、後から屋号を決めてその屋号名を利用するケースが多く、そのことを通知するのを忘れているケースが見られます。こういった問題が郵便物の返送に繋がります。


個人事業主の方で屋号を変更された場合、その旨を迅速にバーチャルオフィスに伝えましょう。
ほとんどのバーチャルオフィス運営会社では、1つの契約につき「1つの名義(個人または会社)」が設定されています。
その契約名義以外の名前で送られた郵便物は、通常受け取られません。
したがって、契約名以外の名義でバーチャルオフィスの住所を利用すると、トラブルを招く可能性があります。

具体的なトラブルの例を挙げてみましょう。
例えば、Aさんが自分が所有する会社Bのために「バーチャルオフィス」を契約しました。
しかし、Aさんはバーチャルオフィスの住所を個人のヤフオクでの荷物受け取り用の住所として使いたいと考え、そのことをバーチャルオフィス運営会社に伝えなかったとしましょう。
その場合、ヤフオクで落札購入した荷物がバーチャルオフィスに届いたとしても、バーチャルオフィスの契約名義と異なるため、受け取りが拒否される可能性が高いです。
個人名義であるAさんは契約の対象外となるため、Aさん個人宛の郵送物は受け取り拒否される可能性があります。これは「バーチャルオフィス」運営会社ごとに契約の解釈が異なるため、契約名義については十分注意が必要です。

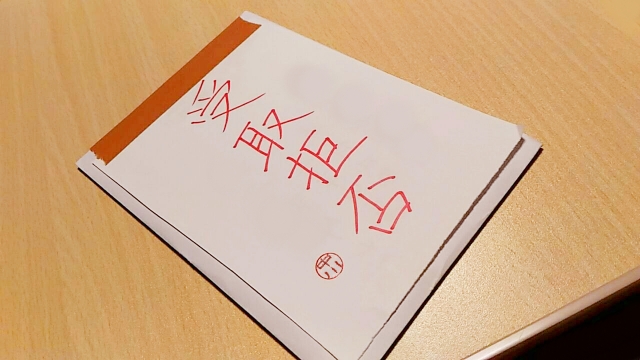

バーチャルオフィスの契約内容を(1契約につき何名義まで利用できるか)事前に確認しておこう
ここで取り上げる問題は、バーチャルオフィスの付属オプションである電話代行サービスを利用した場合のものです。
電話代行サービスは、契約者宛にかかってくる電話をオペーターが受け、要件を確認して契約者に伝えるサービスです。
電話代行サービスでは、「緊急対応が必要なクレームやお客様からの電話」が時折問題になることがあります。

緊急のクレームを投げかけるか、あるいはそのような事態で電話をかけてくる人々は、電話代行オペレーターをバーチャルオフィス契約者の会社の社員だと誤解することがしばしばあります。その結果、「電話代行オペレーターに直ちに対応するよう求める」ケースが生じます。
しかし、このような場合でも、オペレーターは担当者に連絡を取る以外の対応を行うことはできません。
だからといって、電話をかけてきた側から見れば、オペレーターが何も対応していないように見えてしまう可能性があり、「社員なのに融通がきかない」といった不満を抱くことがあります。

バーチャルオフィスでは、電話転送サービスというものが提供されています。このサービスの電話番号はNTTなどの電話会社から取得しますが、ほとんどの場合、新規に発行された電話番号ではありません。
過去に他の会社や個人が利用していた「リサイクル」された電話番号を使用することが一般的です。
ただし、これらの番号は直近で使用されていたものではなく、一定期間使用されていない電話番号となります。そのため、以前の利用者宛の誤通話がかかってくることはほとんどありません。

しかし、問題が生じるのはインターネットにおいてです。
旧電話番号の利用者は、移転、引越し、廃業、倒産等の理由でその電話番号を解約することが一般的です。しかし、会社のウェブサイトがまだ存在し、その上に電話番号が掲載されていたり、移転しても電話番号が更新されていないケースがあります。さらには、ウェブサイト以外のポータルサイトなどに旧電話番号と旧会社名が記録として残っていることもあります。
現代ではインターネットで情報を検索することが一般的なため、電話番号を検索した際に、以前の旧電話番号の会社や個人と何らかの関連があると誤解される可能性が否めません。
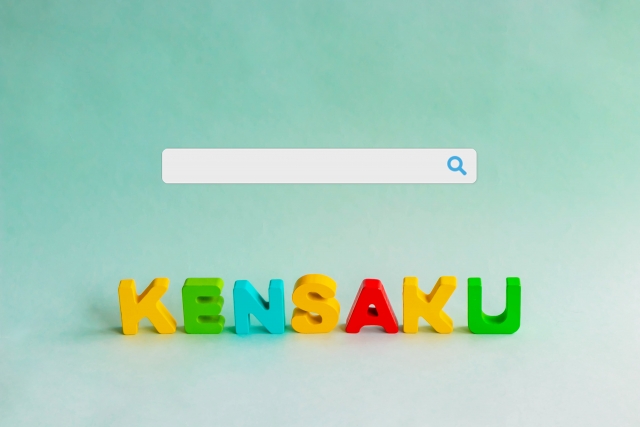

転送電話や電話代行を申しこんで電話番号が提供されたら、必ずネット検索してみよう

バーチャルオフィスの事業は、一度顧客が確定すると収益が安定するストック型ビジネスモデルであり、急激に売上が伸びるような業種ではありません。しかしその一方で新規参入も多く、競争が激化しています。その結果、毎年数社のバーチャルオフィスが閉鎖や撤退を余儀なくされています。
このようなバーチャルオフィスの倒産や閉鎖が起こった場合、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

1つ目の影響は、印刷物の再印刷やウェブサイトの変更です。もしバーチャルオフィスが閉鎖した場合、その住所を利用することができなくなるため、他のバーチャルオフィスに切り替えるか、新たに賃貸オフィスを借りる必要が生じます。
その結果、「会社案内」「名刺」「営業資料」の再印刷や、ウェブサイトの住所変更が必要になり、それに伴う費用が発生します。また、顧客への住所変更の通知なども必要となり、手間と時間がかかります。

2つ目の影響は登記の変更です。
もし「バーチャルオフィス」を法人登記の住所として使用していた場合、新たな住所への登記変更を申請する必要が出てきます。この登記変更には司法書士への依頼費用や登記変更費用など、追加の費用が発生します。
一般に、会社の寿命は約30年と言われています。バーチャルオフィスに限らず、全ての会社はいつかは終わりが来る可能性があります。したがって、そのようなリスクを事前に考慮しておくことが重要です。

バーチャルオフィスは費用も安く契約できるため、詐欺目的の輩や悪徳業者に利用されるケースがあります。
現在バーチャルオフィスの契約は収益防止移転法などの法律に定められており、顔写真入りの身分証明書や所定の手続きを踏まないと契約できないようになっております。
そのため昔に比べてれば犯罪で利用されるケースが減りましたが、クレームの多い悪徳業者や詐欺に近いグレ―ゾーンの企業の利用は今でもあります。

警察沙汰になる例は本当に稀ですが、過去には振込詐欺集団などに利用された新聞などマスコミで報道されることもありました。
事件の深刻さにもよりますが、メディアで報道されると、詐欺に関与した住所がSNSやインターネット上で拡散されるリスクがあります。バーチャルオフィスの住所は共用されるため、問題のある業者が1件でも存在すると、同じ住所を使用していた他の企業も影響を受ける可能性があります。
当然当社を含め、他のバーチャルオフィス運営者も法律に則り、厳しい審査をおこなった上で契約しているところが大半ですが、悪徳業者も非常に巧妙な手口で契約するので、防ぎ切れないところもあります。
バーチャルオフィスのトラブルの傾向を挙げるとやはり一番多いのが郵便物関連だと思われます。 以下の点は特に大事だと思いますので、今後バーチャルオフィスを契約された際は留意しておくことをお薦めします。
参考までに、弊社はこれまで11年間の実績がある老舗バーチャルオフィスです。
弊社が提供する「住所のみのバーチャルオフィス格安コース」なら法人登記OK、郵便転送月4回以上、有人受付対応もありで月額1,955円~です。「コスパが非常に良いと」お客様から評価も頂いております。もしバーチャルオフィスのご利用をお考えなら是非ご利用くださいませ。